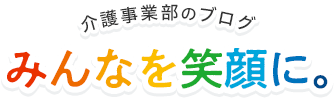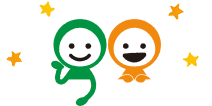2025.08.29
寺田の夏祭り、大盛況とちょっと学び
障がい支援課の谷田です。
先週ご案内した「寺田の夏祭り」は、おかげさまで大盛況に終わりました。
私もアミティスマイルのブースで、はちみつドリンクの販売をお手伝い・・・と言っても、氷を砕いたり、カップを並べたり程度でしたが。
当日は、暑さもあって大人気!!なんと19時前には完売となりました。
今年買えなかった方、本当に申し訳ありません。
来年はぜひ、お早めにご来店くださいませ。
さて、お仕事の方ですが・・・
介護保険の世界に長く浸っていた私にとって、障がい支援の分野はまだまだ驚くことばかりです。
制度や基準は本を読めば理解できますが、「どうケアを行うか」という理論の奥深さは本当に難しいですね。
と言うことで、今週から、ABA(応用行動分析)の本を読み始めました。
ABAとは、人の「行動」に注目し、その行動が起きるきっかけや結果を分析することで、より望ましい行動を増やしていく考え方です。
「レスポンデント条件づけ」は、いわば「パブロフの犬」のように刺激と反応が結びつく現象。
そして、スキナーが体系化した「オペラント条件づけ」では、人の行動は“その結果”によって必ず強化されたり、弱化されたりする仕組みになっています。
例えば「褒められるとやる気が出る」は“正の強化”、
「叱られるのが嫌で別の行動をとる」は“負の強化”。
こうしてみると、私たちの日常の多くがオペラント条件づけの繰り返しでできていると気づかされます。
・・・とはいえ、ここに至るまでにイヌ、ネズミ、ネコ、ハト、ウサギ、サルなど、数々の動物たちが実験台として大活躍(?)してくれた歴史があるわけです。
彼らの“協力”なくして、今の学問はなかったと思うと、ちょっと感慨深いですね。
まだまだ理解は浅いですが、支援に活かせるように「環境や関わり方を工夫して、自然と行動が変わっていく」という視点を持ちたいと思っています。
ちなみに私は、レスポンデント条件づけで「〇〇さんを見ると心臓がドキドキします」。
(さあ、〇〇は誰でしょう。そしてドキドキする理由は何でしょうか?)
今週末も少しずつ読み進めようと思います。
ABAに詳しい方、ぜひご指導ください!
【おまけ】
無事に50歳になりました。
どうしてもプレゼントを贈りたいという“物好きな方”は、第二恵光の事務所もしくはアミティホームまでお願いしますm(_ _)m